アフリカでバイオ燃料の原料作物農園を展開。次世代バイオ資源活用と、途上国の産業育成地盤整備の実現めざす
日本植物燃料株式会社
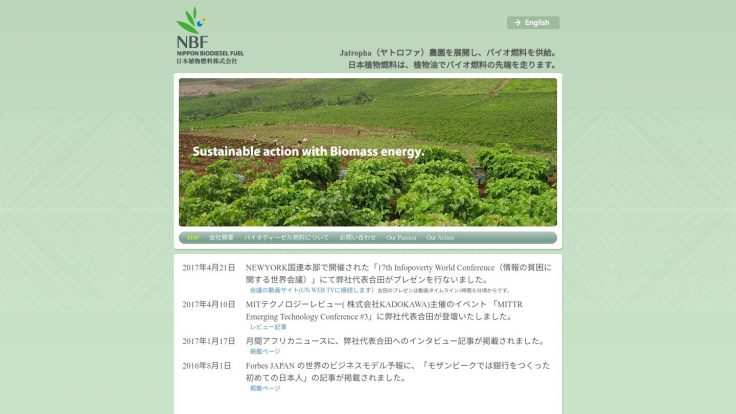
画像取得先: http://www.nbf-web.com/japanese/index.html
会社概要・事業内容
会社概要
Jatropha(ヤトロファ)農園を展開し、バイオ燃料を供給するベンチャー。2008年からフィリピンにおいて、Jatrophaの試験栽培をスタート。今ある森林伐採をせずに、バイオディーゼル・植物油を安定供給できる体制を整えることを目的としている。次世代に通用する、バイオマス資源の活用にむけて、先駆的に努力しつづける。
2000年設立よりバイオ燃料の原材料植物の研究開発を実施。その成果を事業化するため2012年に東アフリカのモザンビーク国に現地法人(ADM)を設立。ADMでは、無電化地域において6,000名の農民組合を組織し、バイオ燃料の原料作物であるJatropha curcas L.(ヤトロファ)の栽培・搾油精製・燃料販売や、米・キャッサバなど農作物の買取り・加工・販売を実施し、これらの販売・買取り拠点も兼ねて小売店舗も運営。
石油ピーク後の社会作りをテーマとして、途上国のpoverty penaltyの解消を事業機会と捉え、産業育成の基盤となるエネルギー・食料・金融分野において地産地消型社会資本整備を事業として実現することを目的としている。
燃料など、州都に比べて僻地ほどより高いコストを払わざるを得ない状況をpoverty penaltyと呼ぶが、これらを外部から持ち込むエネルギーではなく、地産地消型のエネルギーとすることで、僻地でも都市部と同等のエネルギー価格を実現し、その地域の豊かさの向上に資することを目指している。地域が豊かになるためには、エネルギー・食料・金融は不可欠な要素と考えており、この3分野に注力している。
- エネルギー
6,000名の栽培組合員に苗木を配布し、畑や家の垣根として植樹してもらう。収穫物を買取り、種子を搾油し、精製して軽油の代替燃料を製造。トウモロコシの製粉業者への販売が主。 - 食料
コメは、籾米を買取り、精米して独自ブランドで販売。その他、キャッサバや魚など村人の要望に応じて各村ごとの特産物を流通させている。 - 金融
電子マネーの導入を開始。これまで穴を掘って隠していた現金を安全に預かる仕組みとして認知されつつある。
Jatropha(ヤトロファ)とは
Jatropha curcas(和名・ナンヨウ アブラギリ)は、熱帯アメリカに分布する高さ5mの落葉低木か小高木。果実は長楕円形で長さ3~4.5cm。種子には有毒の成分があり、下剤や吐剤に使用される。種子油は石鹸、機械油の原料となる。
アフリカをはじめ世界30カ国以上で栽培されており、主な目的は、砂防の為の垣根や緑化事業。果実の中の種を絞り、油を取り出しランプ用の油、ディーゼルエンジン用燃料、石鹸などに使用する。また、絞りかすはシーズケーキと呼ばれ有機肥料として利用。世界でも先進的にJatrophaに取り組んでいる国、インドでは、インド鉄道の2500kmの軌道両側にJatrophaを植樹したり、またダイムラー・クライスラー社の支援によるプロジェクトなどを積極的に行っている。
主な事業内容
- 植物油の輸入販売事業
・バイオディーゼル製造販売
・植物原油の卸販売
・火力発電所、工場への植物燃料販売事業
・印刷インキ溶剤販売事業
・その他、化粧品、食品、洗剤メーカへの植物油販売事業 - 植物油の研究開発事業
- エネルギー作物のプランテーション経営
- エネルギー作物の搾油精製事業
- 排出権取引に関する派生商品の販売
Jatropha油の販売
Jatropha精製油、およびJatrophaバイオディーゼル油、搾油用種子、絞りかすなどの副産物を含めて製造・販売
Jatrophaの優良品種・栽培技術開発
フィリピンの自社農園にて、多収量・多油量の優良新品種、および栽培環境に応じた最適栽培技術を研究開発中
Jatrophaの副産物利用技術開発
Jatropha油を低コストで安定供給させるために副産物の有効利用を促進する各種新技術の開発
経営者プロフィール
代表取締役 合田真
(同社Webサイトおよび同社Wantedly掲載情報を基に当社編集)
